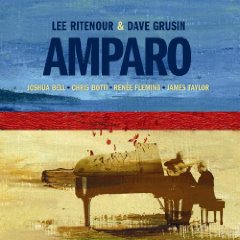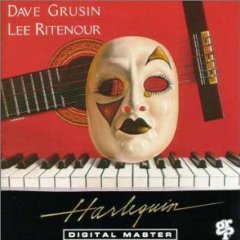|
「ミスター・パーフェクト」の異名を持つ、コンテンポラリー・ジャズの頂点に立つギタリスト、リー・リトナー。フュージョン全盛期には、ラリー・カールトンと人気を二分したスーパー・ギタリストだ。そのたぐいまれな才能をいち早く発掘し、華やかなキャリアの道筋をつけたのが、デイヴ・グルーシンである。グルーシンは、ピアニスト/キーボーディストのみならず、コンポーザーとして『恋に落ちて』『トッツィー』を始めとする数々のヒット映画の音楽を手がける一方で、フュージョンの名門レーベル、GRP創設者の一人として、シーンを牽引してきた重鎮。
そんな二人が手を結んで新たな音楽的地平線を切り開いたのが、2000年の『トゥー・ワールド』だった。ストリングス・オーケストラをバックに、ジャズ・サイドの二人が自分たちの感性でクラシックにアプローチしたこの優美なアルバムは、クラシカル・クロスオーバーというジャンルに先鞭をつけることになった。その第二弾『アンパロ』をリリースしたばかりのリトナーとグルーシンが来日、世界に先駆け、ついに新日本フィルでオーケストラとのコラボレーション・ライブを実現することになった。9月22日、公演を控え来日中のリトナーに話を聞いた。
(工藤 由美)
|

|
Lee Ritenour
(photo by Ryo Shinoda)
|
|
―最初に、『トゥー・ワールド』の続編とも言える『アンパロ』のリリースの経緯について教えてください。
リー・リトナー(以下LR):
前作の『トゥー・ワールド』は大ヒットというわけじゃないけど、コンスタントに売れ続けて、結果的にクラシカル・クロスオーバーのチャートに1年間も留まることになった。今も売れ続けていて、レコード会社としては成功したアルバムだった。数年前、会社から「いつになるか確約は出来ないが、もう一枚作りたいと思っているんだが、やる気はあるかね」とたずねられた。僕等に異論があるはずがなかった。オーケストラとの共演は、ビッグチャレンジであり、いわば音楽家の夢。莫大な予算が要るので、そうそう機会があるわけでもない。でもその話があってから、あっという間に月日が流れ、ようやく実現に漕ぎ着けたのが2年前。そこから制作に1年半を要した。ジェームス・テイラーやルネ・フレミング等超多忙のアーティストをゲストに招聘したので、その調整に手間取った。諦めるという選択肢もあったけど、この手の作品はタイムレスだから、あせらず機が熟すのを待とうということになった。おかげで自分たちが胸を張れる作品になった。妥協しなくてよかったよ。
―クラシカル・クロスオーバーというジャンルが確立されているのですか?
LR:
LR:それに類したものはあったけど、クラシックとジャズという意味では、結果的に『トゥー・ワールド』でやったことが時代を先駆け、トレンドを作ることになった。その後、ジョシュ・グローバンなんかがどんどん出てきたからね。この手の音楽は頻繁にラジオでオンエアされるわけでも、たくさんコンサートが打てるわけでもないのでプロモーションがむずかしい。でもリスナーの多くが大人だし、一過性の音楽ではないからね。
―本国ではオーケストラとコンサートを行っているのですか?
LR:
これから。新日本フィルとの共演が世界初になる。今回は普通のクラブでのライブもあるし、演奏曲目がすごく多いので、練習が大変。プレッシャーを感じるけど、これはいい意味でのプレッシャー。毎晩東京で遊びまわるわけにはいかないな(笑)。怠けないで練習しないと。
実はデイヴと一緒に日本でオーケストラと共演するのはこれが初めてではない。今のリスナーがどれぐらい覚えているかわからないけど、80年代前半に、スティーヴ・ガッド、アンソニー・ジャクソン、エリック・ゲイルなんかと一緒に武道館でコンサートをやっている。LAオールスターといったようなドリーム企画で、LAとNYのベスト・ミュージシャンを集め、日本のオーケストラと共演するというイベントだった。その頃は、会場のせいもあるのだろうけど、弦がいまいちでね。その点、新日本フィルは今、世界のトップクラスと聞いている。彼等に相応しい演奏ができるようベストを尽くすよ。
―『トゥー・ワールド』と『アンパロ』の違いは?
LR:
サウンドは似ているかもしれないけど、アプローチは全然違う。今回はもっとリリカルなものにしようというのがあって、最初に手がけたデイヴのオリジナルのダンス組曲と僕の<エコー>が、アルバムの基調になった。フレンチやブリティッシュのワールドミュージックのフレーバー、特にラテン色の濃いものにというイメージが出来上がって、そこからは自由にやった。前作は逆で、最初にオーケストラとバッハを録音し、それを出発点にした。そのときデイヴは「可能な限りクラシックのルールに忠実に」と言っていた。でも『アンパロ』をスタートさせるに当たって僕は言ったよ。「デイヴ、僕等はクラシックのミュージシャンじゃないんだ。僕等がどれほど彼等のルールに忠実にプレイしたところで、クラシック界が僕等を認めることは絶対にないんだ。そうであるなら僕等は僕等のルールでプレイしようじゃないか。タンゴはタンゴらしく、クラシック風のタンゴではなく、僕等が考えるタンゴを演奏すればいいじゃないか」と。
―なるほど。選曲にも苦労があったのでは。
LR:
よく知られている曲と無名の曲と半々ぐらい。ピアノとギターとストリングスに合うものをと探していると、かなり限定される。それにどちらにしても編曲しなければならない。そもそもアレンジが存在しないわけで、テクニックとイマジネーションが必要とされる。デイヴが真価を発揮したよね。
―オリジナル曲の<エコー>は、このアルバムのために書き下ろしたのですか?
LR:
そうだよ。最初はストリングスと一緒にとも思ったのだけど、二人だけでやってみたら、それでサウンド的にはまったく過不足なかった。デイヴと僕の間にはサムシング・スペシャルがあるけど、それがここにも現れている。ピアノとギターのサウンドが溶け合って、言われなければ、たった二人で演奏していることにさえ気がつかないと思うよ。ストリングスが不足しているなという印象も受けないと思う。
―お互いに特別な存在なのですね。
LR:
本当に深い縁があるよね。デイヴと対面したのは18歳のときだけど、それ以前からデイヴ・グルーシンの名前は知っていた。TVを見ていて、いい音楽だなと思ったら、それを作曲していたのがデイヴだった。それからコンポーザーとして意識するようになった。15、6歳のとき、大好きなジャズ・ギタリストのハワード・ロバーツが出演するというので、父にジャズ・クラブに連れて行ってもらった。そこでプレイしていたのがデイヴで、サインをもらった記憶がある。そのときのサックスが18歳のトム・スコットで、かっこいいなと思ったよ。
それからしばらくして僕は『ダンテ』というクラブに通い始めた。そこはスタジオミュージシャンのたまり場で、毎晩エキサイティングな演奏が行われていた。毎週月曜日がギターナイトで、バニー・ケッセル、ジョー・パス、レス・ポールといった憧れのプレイヤーが出演するので、欠かさずに通っていた。
話がちょっと脱線するけど、数年前にキャピトルレコードでレスにばったり会ったんだけど、彼の記憶力は普通じゃない。その頃すでに90歳になっていたと思うけど、すごい記憶力なんだよ。僕が「若い頃、お目にかかったことがあるんですよ」と言うと、「そうだったね。覚えているよ」というので、「ご冗談を」と言うと、「ダンテのマンデーナイトを見に来ていたよね。キミはそのときまだ19歳だったけど、ギタリストとしてすでに評判になっていた」というわけだよ。ぶったまげたね。ジョン・ホプキンス大学が研究対象にしているぐらい、レスの記憶力はずば抜けている。

|
Lee Ritenour
at Blue Note Tokyo
(photo by Takuo Sato)
|
―ハハハ。今もお元気でライブ演奏なさっていますが、それが若さを保つ秘訣かもしれませんね。
LR:
本当だね。それでデイヴの話に戻ると、あるときリナ・ホーンのギタリストとしても活躍していたガボール・ザボのショーがキャンセルになり、ダンテのオーナーから電話がかかってきた。「突然で申し訳ないが、今夜のギターナイトだが、キミのグループで演奏できないか」と。もちろん答えは「YES」さ。ところがバンドもへったくりもない。大急ぎでメンバーをかき集めて、その場しのぎでショーを乗り切った。幸運だったのは、その晩、またまドラマーのハーヴィー・メイソンが見に来ていたんだよ。バンドのメンバーが、「すげえ、ハーヴィー・メイソンが来ているぜ」というので、「誰だよ、それ」「お前知らないのか?ハービー・ハンコックのドラマーで、<カメレオン>を作った奴だよ」って。
ショーが終わると、ハーヴィーが僕のところにやってきて、「さっきダニー・ハサウェイの曲やっていたけど、譜面あったらコピーさせてくれないか」と言うんだよ。で、僕は少しばかり緊張しながら「どうぞ」と言って差し出すと、「オレと一緒にバンドやってみる気はないか。キーボードはデイヴ・グルーシンだ」と言われた。ウソだろうって思ったよ。
―それから長い付き合いが始まったのですね。
LR:
そうなんだ。デイヴには、どれほど助けられたかわからない。その頃のデイヴはTVや映画の音楽を数多く手がける超売れっ子で、すでにエスタブリッシュされた存在だった。そのデイヴが20歳の無名のギタリストを盛んに使っていたわけだよ。グルーシンが使うぐらいだから、よほど上手い奴なのだろうと思われたんだろうね。それで次々と仕事が舞い込むようになり、気がつくと多忙なスタジオミュージシャンのひとりになっていたというわけさ。
―今回、ベースのエイブラハム・ラボリエルも一緒ですが、彼との付き合いもかなり古いですよね。
LR:
そうそう。エイブの最初の印象も強烈だったな。あれはヘンリー・マンシーニのレコーディングだった。マンシーニがスタジオに入ってきて、こういうわけだよ。「みんなにオハイオ州クリーヴランドからやってきた、ベースのエイブラハムを紹介する」と。エイブはメキシコ出身なんだけど、奥さんの仕事の関係でクリーヴランドに住んでいた。クリーヴランド出身のマンシーニが気に入って、地元でよく使っていたらしいんだな。
入り口の方に目をやると、ポンチョを着て、メキシコのださいゴヤ・ベースを抱えた、奇妙な風貌の男が立っているじゃないか。こいつ、いったい何もの?って感じだった。
それは月曜の朝10時ぐらいの出来事で、みんなブルーマンデーで少々退屈していた。レコーディングが始まった。1曲目の最初のソロは、エイブラハムだった。その男は自分のソロの番になると、やおらイスから立ち上がり、ぴょんぴょん飛び跳ねながら全身でプレイするわけだよ。開いた口がふさがらないってこういうことを言うのだろうね。眠気が一度で吹き飛んだよ(笑)。それがきっかけでエイブと仲良くなり、FRIENDSHIPをスタートさせたんだ。
―グルーシンにしてもラボリエルにしても、今も友情が続いているわけですね。
LR:
もちろんだよ。ベスト・フレンドとこうして一緒に音楽がやれることを本当にうれしく、また幸せに思っている。
リトナー・グルーシンのその他の主な共演盤
|